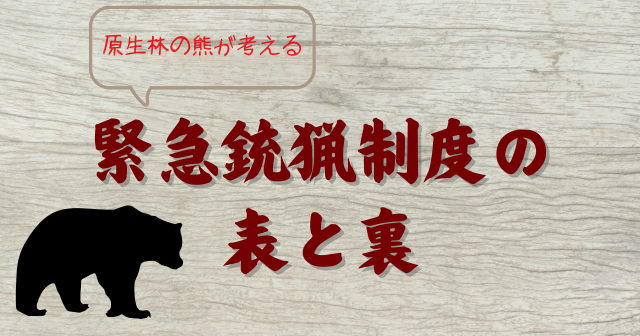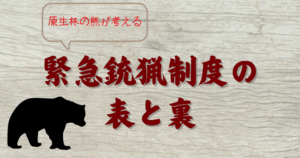ご存じの方も多いかと思いますが、今問題となっている熊対策にかかわる新しい制度が、2025年(令和7年)9月1日から施行されました。それが「緊急銃猟制度」です。
今回は、この制度を分かりやすく解説、現状の問題点や国民が直面している危険についてまとめていきたいと思います。
緊急銃猟制度とは?
緊急銃猟制度(きんきゅうじゅうりょうせいど)とは、クマやイノシシが住宅地などの「人の日常生活圏」に出没し、人命や身体に危険が迫っている場合に、市町村長の判断で緊急に銃器による捕獲(銃猟)を可能にする制度です。
近年、クマなどの市街地への出没が全国的に増加し、人的被害が深刻化している事態を受け、迅速な対応を可能にするために創設されました。2024年(令和6年)に鳥獣保護管理法が改正され、2025年(令和7年)9月1日から施行された比較的新しい制度です。
今までは?
では、今まではどのような決まりや仕組みになっていたのかというと、緊急銃猟制度が施行される前は、市街地などにクマやイノシシが出没した場合、主に「有害鳥獣捕獲」の制度や「警察官による対応」に基づいて対処されていました。
農作物や生活環境への被害(またはその恐れ)がある場合に、都道府県知事や市町村長の「許可」を得て、鳥獣を捕獲する制度。
ただ、手続きに時間がかかるため、市街地に熊が出没したような一刻を争う事態では時間的余裕がなかった。
また、被害の発生が前提のため、熊が市街地を徘徊しているだけで人的・物的被害がなければ許可を出すのが難しかった。
人の生命・身体への危害が差し迫っている場合、警察官は危害を防止するために武器(拳銃など)を使用することが認められている。
ただ、警察官が通常装備している拳銃は熊を確実に仕留めるには威力不足であり、かえって動物を興奮させてしまうリスクが指摘されていた。
また、警察官は治安維持の専門家であるものの、野生動物の生態や捕獲の専門家ではなく、大型動物への対応は猟友会のハンター(猟師)の専門領域のため、警察官だけでの対応には限界があった。
今まで、市街地に熊が出没した際の対応の流れは以下が一般的でした。
- 住民から警察や市町村に通報が入る。
- 警察官や市町村職員が現場に駆けつけ、住民の避難誘導や現場の封鎖を行う。
- 並行して、市町村が地元の猟友会に協力を要請する。
- 猟友会のハンターが現場に到着する。
- 市町村が(緊急的に)有害鳥獣捕獲の許可手続きを行う。
- ハンターが捕獲(銃猟)を実施する。
このような流れだと、4のハンター到着と、5の捕獲許可に時間がかかってしまうのが大きな問題点でした。
当然ですが熊は生き物なので動きますし、捕獲されるのを待ってはくれません。そのため、「警察をはじめとした関係者が市街地に現れた熊を見守っている」ような状況になっていたのです。
この「対応の遅れ」が、クマが市街地を移動し続け、被害を拡大させる一因となっていました。
緊急銃猟制度の目的と特徴

この制度の最大の目的は、差し迫った人への危害を緊急に防止することです。
実施の主体は「市町村長」です。地域の状況を最もよく把握している市町村長が、緊急対応の必要性を判断し、実施を指示します。実際の捕獲は、市町村から委託を受けた猟友会などのハンター(捕獲者)が行います。
ただし、この制度が適用されるのは「人の日常生活圏」に限定されます。あくまで住居、生活道路、商業施設、学校、農地、公共交通機関など、人々が日常的に活動するエリアに限られます。
4つの条件
緊急銃猟は以下の4つの条件を満たしている必要があります。
- 人の生活圏への侵入またはその恐れがある
- 措置を緊急に講ずる必要がある
- 銃猟以外の方法では困難である
- 発砲によって人に被害が及ぶ恐れがない
対象となる鳥獣(危険鳥獣)
緊急銃猟の対象は、法律(鳥獣保護管理法施行令)で定められた以下の「危険鳥獣」に限られます。
- ヒグマ
- ツキノワグマ
- イノシシ
通常の狩猟や有害鳥獣捕獲との違い
通常の狩猟は「狩猟期間中」に「狩猟鳥獣」を対象に行うものです。また、農作物被害などを理由に行う「有害鳥獣捕獲」は、事前に都道府県知事などの許可が必要です。
緊急銃猟制度は、このような手続きを待てない「緊急事態」において、迅速な人命保護を最優先する点で大きく異なります。
緊急銃猟実施時の安全確保
緊急銃猟は市街地などで行われる可能性があるため、市町村は住民の安全を最優先に確保する措置を講じます。
- 通行規制:現場周辺の道路を一時的に封鎖します。
- 避難指示:現場の状況に応じて、「屋外避難(その場から離れる)」や「屋内避難(建物内にとどまる)」を指示します。
- 広報活動:防災無線、広報車、SNSなどで住民に危険を知らせます。
もし緊急銃猟の現場に遭遇した場合は決して近づいたり見物したりせず、速やかにその場を離れ、警察官や市町村職員の指示に従ってください。
屋内避難の指示があった場合は、窓から離れた場所(廊下など)に待機することが推奨されます。
現在の熊の状況と自然環境

2025年10月現在、毎日のように各地で熊出没と熊による被害(人的・物的・ペット等含む)が報道されています。
毎日TVやネットニュースを見て、または自治体からのお知らせによって熊への恐怖を感じてお過ごしの方も多いかと思います。
山の状況
2025年の秋は山に餌が極端に無く、熊は山にいない状態です。これは2023年と同じ状況で、きのこ採りの人も「熊の気配が少ない」と証言しています。
(ただし、これは岩手県での状況です。地域によっては「狩った熊は太っていて、山に餌がないわけではない」と言う猟師もいます。)
熊の数は増えているはずなのに、山に気配がないということは、山以外の場所(人の生活する場所やその近く)に熊がいるということです。
出没の原因
昨年(2024年)秋に餌が豊富で子熊が多く産まれたものの、2025年は餌を求めて民家近くに出没しています。
餌が豊富にあるか否かは別として、熊の数が増えれば必要な餌の数も増えます。山の餌の量が増えた熊に対して十分な量でない可能性も考えられます。
山に餌がなければ、餌を求めて人里に出てくるのは当然と言えるでしょう。
被害状況
毎日の報道でご存じかと思いますが、町や里、畑や果樹園での被害が多発しています。
空腹がひどいため人間や犬さえも襲うようになり、住居侵入や飼い犬が襲われる事態になっています。熊は一度味を占めると、またその場所へやってきます。
天候不順
なぜこのような事態になったのか。春の遅霜、低温や高温、昆虫の減少などが、木の実の不作に影響しています。開花時期の低温や、極端な高温によって木の実の出来が左右されます。
それだけでなく、ドローンでの農薬散布なども影響しているかもしれません。農薬の濃度が高くなってしまう、または必要以上の場所に農薬を散布してしまうと昆虫も激減します。
今まで昆虫の力を借りて受粉していた木が、昆虫の激減によって受粉する数が減る→結果として木の実が減る、といった仕組みになります。
地域差
熊の出没が多い地域では、3月1日から10月31日(猟期外)の有害捕獲が少なく、猟友会が弱体化している特徴があります 。
山林が近くにあるところであっても出没が少ない地域は、大型獣を狩れるスペシャリストが存在しています。
住民の安全と被害

何よりも重要視すべきは、住民の安全性です。
「一歩外に出れば熊がいるのではないかと怖くて最小限の外出にしている」「子どものことを思うと一人で登下校させられない」といった声も聞かれます。
- 被害の深刻化:玄関先で襲われるケースや、倉庫・住宅内部まで物色されるケースがあり、死亡事故も複数発生しています。
- 避難と再発:夜間に公民館へ避難したところ、その夜に台所を荒らされたという方もいます。一度荒らされると3日程度は被害が続く傾向があります。
- 危険な熊の発生:
- 人が襲われる事案が発生すると、「人喰い熊」が完成し、その個体が捕殺されるまで被害が連発します。
- 「犬喰い熊」も同様に連発し、犬を喰う熊は人も襲う傾向があります。
\人喰い熊に関してはこちらを確認/
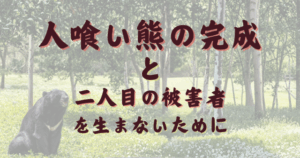
緊急銃猟制度における関係各所の対応と問題点
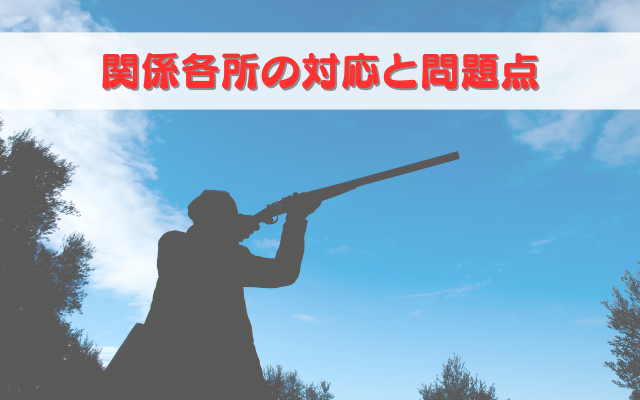
この制度は、緊急時に市町村長や都道府県知事が迅速に許可を出せる特例制度ですが、現状としては連携が取れていない様子がうかがえます。
県 (都道府県)
県が積極的に運用方法を示さないと、市町村の動きや準備が遅れてしまいます。県知事や県議会が迅速に動かないと市町村長の判断も遅れ、結果として緊急銃猟制度の運用が遅れるのは当然の結果です。
国・県・市町村は縦社会のような関係になっていますので、市町村町の判断で緊急銃猟を行えるといえど、やはり県の動きが重要と言えるのではないかと思います。
市町村
緊急銃猟制度の運用に対して、市町村が県の動きを待って様子をうかがっている、今までにはなかった制度のため手探りで他の市町村の動きをうかがっている、といった状況であれば、当然ながら準備が遅れます。
「上はなんて言うのかな?」「他のみんなはどうしてる?」「もしも自分が先に動いて批判されたら…」と周りの様子を気にすればするほど、住民の安全が軽視されてしまいます。市町村長の強い意思がなければ、準備や運用は遅れるでしょう。
警察
以前は警察が危険と判断すれば許可を出して緊急捕獲が行われていました。しかし、制度が9月から運用開始されてから、警察は市町村長の判断を優先しようとしているように映ります。
今は責任の所在が市町村長と二分する形になっていて、警察の責任が低下したようにも見えます。
警察だけではなく県・市町村も含め、できれば何かあった時の責任を取りたくない…といった心理が働いているのではないでしょうか。
猟友会
猟友会は緊急銃猟制度に関して、市町村長や警察の指示待ちで、主体性がありません。過去のトラブルや事案(砂川町猟友会トラブル※1、町議会議長の暴言事案※2)を受け、逃げ腰になってるようです。
※1砂川町猟友会トラブル:北海道砂川市で発生したヒグマ駆除時のトラブルが発端となっています。ヒグマを駆除した猟友会員が発砲行為を巡って警察に書類送検され、その後猟銃所持免許が取り消しされました。これに対しで猟友会は不当な処分として抗議、駆除要請の受諾を拒否する動きが広がりました。
※2町議会議長の暴言事案:北海道積丹町の町議会議員宅裏に設置された箱罠に熊が捕獲され、駆け付けた地元のハンターに猟友会員にたいして高圧的な態度を取り「こんなに人数が必要なのか。金貰えるからだろ。俺にそんなことするなら駆除もさせないようにするし、議会で予算も減らすからな。辞めさせてやる」などと言ったとされる事案です。
銃刀法違反※3で猟銃を取り上げられることを避けたい気持ちを優先しているハンターも多いのではないでしょうか。砂川町猟友会トラブルの影響もあり、猟友会は警察に対しても懐疑的です。
※3銃刀法違反:「銃砲刀剣類所持等取締法」に違反して、銃や刀剣類、一定の刃物などを所持・携帯することです。正当な理由なくこれらを携帯すると、「業務その他正当な理由」がない限り、違反となります。そのため、猟師は市町村や警察の指示や許可なく、人の生活圏で猟銃を持ち歩くことは許されません。
2024年より2025年のほうが、警察の責任の低下と市町村長への権限付与で、猟友会は動きづらくなった事実があります。
求められる対応
県知事、特に市町村長は、住民の安全を第一に捉え、早急に行動しマニュアルを作成することが急がれます。
関係各所がそれぞれ主体性を持つこと、他の行動を参考にするという甘えを捨てることが必要だと考えます。
私たちにできること
熊対応について、緊急銃猟制度の運用について、関係各所にもどかしい気持ちでいる方も多いでしょう。また、不満をお持ちの方もいらっしゃると思います。
ただ、私たちにできることは、自分の身や家族の身を、自分たちで守ることです。
そのためには、自治体からの熊出没のお知らせやTV・インターネットなどのニュースなど、熊の情報に敏感になっていただきたいと思います。
熊に会わないための対策や出会ってしまったときの対応についても知識を持っておきましょう。
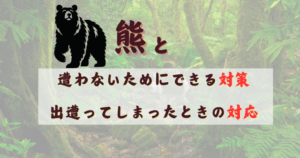
また、熊から身を守るためのグッズ用意を検討してみてください。熊対策グッズには、熊鈴や熊スプレー、熊撃退ポール、ヘルメットなど様々なタイプのものがあります。
原生林の熊工房でも、オンラインショップで熊対策グッズを販売しております。
さらに、緊急銃猟の現場に遭遇した場合は速やかにその場を離れ、警察官や市町村職員の指示に従いましょう。屋内避難の指示があった場合は、窓から離れた場所(廊下など)に待機してください。
賢く熊対策を行い、家族や自分の身を守っていきましょう。