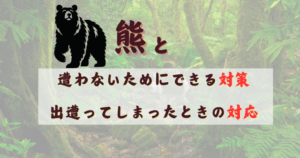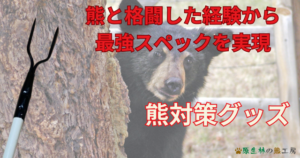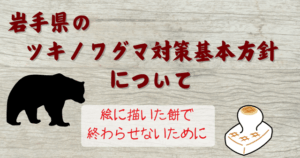令和7年11月5日、岩手県は「ツキノワグマ対策基本方針」を策定しました。全国的にクマの出没や人身被害が増加し、県内でも住宅街や学校付近での出没が相次ぐ中、県民の安全を守るための対策強化が急務となっています。
しかし、策定された方針は本当に十分な内容なのでしょうか。
今回は熊と格闘した経験のある私(原生林の熊/佐藤誠志)が、発表された基本方針の概要を紹介するとともに、その実効性を高めるために必要な視点について考察します。
岩手県が策定した「ツキノワグマ対策基本方針」とは?
岩手県が策定した「ツキノワグマ対策基本方針」は、クマ被害対策を効果的に推進するために策定されたもので、国の新たな方針(指定管理鳥獣への追加、規制緩和など)も踏まえ、これまでの取り組みをさらに強化するものです。
特に令和7年10月以降、人の生活圏での出没が相次ぎ、県民の命を脅かす状況が現実のものとなる中、人とクマとのあつれきを軽減する総合的な対策が求められています。
策定の背景|全国的な被害増加
全国的にクマの出没件数や人身被害が増加傾向にあります。国は令和6年4月にクマを指定管理鳥獣に追加し、令和7年9月には市街地での銃使用の規制緩和を含む改正鳥獣保護管理法を施行しました。
このような国の動きと連動し、県としての対策を強化する必要がありました。
岩手県の現状|深刻化する出没
岩手県では、第5次ツキノワグマ管理計画(令和4年3月策定)に基づき、個体数管理や被害防除対策を市町村と連携して進めてきました。
しかし、方針に示された通り、令和7年度は10月末時点で死亡事例5件を含む33件34名もの人身事故が発生しており、従来では考えにくかった場所での出没が多発し、より一層踏み込んだ対策が不可避な状況となっています。
基本方針が掲げる「5つの柱」
今回の方針では、総合的な対策の強化を図るため、次の5つの柱で構成する取組を効果的に推進するとしています。これらは対策の方向性を示すものです。
- 人の生活圏への出没防止
クマを人の生活圏に近づけないための環境整備や、誘引物(柿や栗、生ごみなど)の管理徹底、緩衝帯の整備を図る取り組みです。 - 出没時の緊急対応
実際に出没した際の迅速な情報共有、通報体制、そして現場での安全確保や追い払い、必要に応じた捕獲体制の強化です。 - クマ類個体群管理の強化
科学的知見に基づき、生息数を適切に管理するための個体数調整(捕獲)や、生息状況のモニタリングを強化します。 - 人材の育成・確保
対策の担い手となる猟友会会員や、市町村職員の専門知識・技術の向上、そして次世代の担い手の育成・確保を進めます。 - 対策の実効性を高める体制の整備等
県、市町村、猟友会、地域住民など、関係機関の連携を強化し、対策が現場で確実に実行されるための体制を整備します。
対策は「絵に描いた餅」で終わらないか?

立派な方針が示されましたが、これが実効性を伴う「食べられる餅」になるかどうかは、これからの具体的な取り組みにかかっています。
方針の「現状と課題」でも「緊急銃猟における安全の確保が困難な場合における捕獲体制を構築する必要がある」と認めている通り、課題は山積みです。
今回示された方針には、現場の実態を反映するために不可欠ないくつかの視点が欠けているように思えてなりません。
抜け落ちている「現場の数字」
最も重要なのは、具体的なデータ分析です。方針では「大規模ヘアトラップ調査」など科学的な生息数推計に言及していますが、対策の実行部隊である現場の「運営能力」に関する分析が抜け落ちています。
どの地域で、どれだけの捕獲が行われ、どこの体制が機能している(あるいは、していない)のかを詳細に把握する必要があります。
| 分析すべきデータ(提案) | 分析単位 | 分析の目的 |
|---|---|---|
| 有害駆除捕獲数 (クマ) | 市町村別・猟友会支部別 | 各地域の対応力の把握 |
| 有害駆除捕獲数 (シカ・イノシシ) | 市町村別・猟友会支部別 | 生態系バランスの把握 |
| シカ罠等への錯誤捕獲数※ | 市町村別・猟友会支部別 | 生息域拡大の実態把握 |
※錯誤捕獲数:意図せずに捕獲された鳥獣の数。例えば、シカを捕獲するはずが間違えてクマを捕獲する、といったケース。
なぜ機能しているか?の分析
これらの数字を精査することで、例えばA市町村のB猟友会は捕獲数が多く、効果的に機能しているが、C市町村のD猟友会は機能が弱まっている、といった実態が見えてきます。
単に数字を出すだけでなく、「なぜA市町村は機能しているのか」(例:報奨金が高い、市町村の支援が手厚い、若手が多い)を調べる必要があります。
機能不全の理由の精査
逆に、機能が弱まっている理由(例:高齢化、報奨金が安く赤字になる、手続きが煩雑)を徹底的に精査しなければ、今後の課題解決や「(4) 人材の育成・確保」の柱に反映させられません。
原因がわからなければそれに対する最も効果的な改善策がとれないのは当然のことです。
現場が大事な理由
「事件は会議室で起きてるんじゃない!現場で起きてるんだ!」ということですね。
どんなに素敵な対策方針を打ち出しても、実際の現場の状況や声が反映されていなければ机上の空論になってしまいます。熊害を減らせないのはもちろん、猟友会をはじめとする現場の不満も溜まる一方でしょう。
クマの生息地「森林行政」への提言は?
クマが出没する根本的な原因の一つは、生息地である森林の環境変化です。
今回の方針では「(1) 人の生活圏への出没防止」の中で、「緩衝帯の整備」や「間伐等を通じた里山林の整備」に言及していますが、これはあくまで対症療法的な「棲み分け」策に留まります。
針葉樹から広葉樹への転換支援
戦後に植林されたスギやヒノキなどの針葉樹林は、クマの餌となるドングリなどが実りません。これらの針葉樹を伐採した後、放置するのではなく、ブナやナラなどの広葉樹林に転換していく政策が必要だと思います。
県は、こうした転換を行う林業関係者に対し、強力な補助支援などを考えるべきでしょう。
| 森林タイプ | クマにとっての価値 | 求められる県の対応 |
|---|---|---|
| 針葉樹林 (スギ・ヒノキ) | 低(餌が少ない) | 伐採後の広葉樹への転換支援(提案) |
| 広葉樹林 (ナラ・ブナ) | 高(ドングリなど餌が豊富) | 保全・育成 |
| 方針にある「緩衝帯」 | 中(棲み分けの境界) | 刈り払い等の整備(方針に記載あり) |
開発事業への県の考え方
また、風力発電所の設置や大規模な太陽光パネルの設置は、森林を伐採し、クマの生息地を分断する要因となり得ます。
こうした開発事業がクマの生態に与える影響について、県の明確な考え方や基準が示されるべきです。
開発で本当にクマの住処が奪われているのか?
「ソーラーパネルの設置が熊の住処を奪っている!熊の住むところがなくてかわいそう!」といった声も聞かれます。
太陽光パネルの設置は大規模な森林伐採のもと行われるケースも多く、いろいろな人の目にとまります。また、緑のなかに広がる黒のパネルは異質にも見えますよね。
もちろん、「人が自然を壊している」といえますが、その一方で、「人が手入れをしていた土地が縮小化している」というのも事実です。
地方の過疎化、高齢化、農業離れなどが理由で、緩衝地帯が森に還っている例が多く見られます。
かつて、人の手が入った里山(下草刈りや定期的な管理が行われていた土地)は、クマの生息地である奥山と人里との間の緩衝地帯として機能していました。見通しの良い環境が、クマが人里に近づくのを防ぐ役割を果たしていました。
ただ、現在は管理が行き届かなくなるケースも増え、耕作放棄地が増加。登記上の地目が「田」となっていたが、何年も使わずにいたため木や草が覆い茂り、行政より「原野」に変えるように連絡があった…という話も実際に聞きます。
熊の住処が減っているのか、増えているのか、境界線が曖昧になっていないのか…しっかりとした数値を出すのも必要ではないでしょうか。
経済損失「観光客減少」への対策は?
クマの出没が連日報道されることは、地域の安全だけでなく、経済にも深刻な影響を与えます。特に観光業へのダメージは計り知れず、この視点が方針から抜け落ちているのは大きな問題です。
注意喚起の「その先」
方針には「(5) 対策の実効性を高める体制の整備 等」の早急に行うべき対策として、「ク 観光客等に向けた注意の喚起と正確な情報の発信」とありますが、これは安全対策に過ぎません。
先日ニュースでも取り上げられていましたが、ツキノワグマがいないとされる千葉への観光客が増加しています。千葉へ観光に行った人に聞くと「本当は他の県に行こうと思っていたが、クマがたくさんいるのではと思い、行先を千葉に変えた」という意見も多々ありました。
「クマが怖いから今は岩手・秋田に行くのはやめよう」という観光客の減少は、すでに現実のものとなっています。この経済損失に対して、県がどう向き合うのか、その先を見据えた対策が必要です。
逆転の発想|クマのテーマパーク構想
岩手県は、不名誉ながら日本一のクマ目撃数を記録しています。この現実を逆手に取り、例えば保護したクマを集めて「世界一のクマのテーマパーク」を構築するなど、中長期的な経済戦略も必要ではないでしょうか。
これは一つの案ではありますが、安全を確保した上で、クマを「厄介者」から「資源」へと転換する発想も求められます。
| 対策の段階 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 短期(方針に記載) | 観光客への注意喚起・情報発信 | 安全確保(必須) |
| 中長期(不足する視点) | 観光客減少による経済損失の試算 | 問題の規模の把握 |
| 戦略的(未来への提言) | 安全を確保した上での観光資源化 | マイナスをプラスに転換 |
対策の担い手「猟師」への視点

5つの柱の「(4) 人材の育成・確保」にも関わりますが、対策の最前線に立つ猟師(猟友会)への支援が具体的でなければ、計画は進みません。
報奨金の明確化と増額
方針には「捕獲従事者への手当や捕獲に係る経費の市町村への支援」とありますが、これは「要望項目」となっており、県としての具体的な増額案が示されていません。
命の危険を伴う活動に対し、十分なインセンティブがなければ担い手は増えません。
| 対象獣 | 報奨金額(提案の一例) | 目的・理由 |
|---|---|---|
| クマ | 40,000円 / 頭 | 危険度に見合った報奨 |
| シカ | 20,000円 / 頭 | クマとの餌の競合を減らす |
| イノシシ | 20,000円 / 頭 | クマとの餌の競合を減らす |
根本原因|シカ・イノシシとの「餌の奪い合い」
県はクマ対策に注視していますが、クマの餌不足の根本原因を見誤っている可能性があります。方針ではシカ・イノシシ対策は「(1) 人の生活圏への出没防止」でわずかに触れられる程度です。
しかし、餌不足は天候不順だけでなく、爆発的に増加したシカやイノシシとの「餌の奪い合い」によって引き起こされています。
シカやイノシシがドングリや下草を食べ尽くすことで、クマが食べる分がなくなり、人里に下りてこざるを得ない状況が生まれています。クマ対策は、シカ・イノシシ対策と一体で講じる必要があります。
いちどは絶滅したイノシシが増えている
岩手県では、明治時代にはイノシシが絶滅したとされていました。実際に30年ほど前には「イノシシを見た」という話を聞いたことがないという声もあります。
しかし、同じ地域で現在は、イノシシによる農作物への被害に困っている人もいます。イノシシは2007年以降、県内各地で目撃されるようになりました。また、サルも同様で、以前は目撃されなかった地域でも、道路を渡る姿などが目撃されるようになっています。
熊問題の裏側で、シカ・イノシシ・サルなどの他の野生動物が増えているのも事実です。となれば、当然、山では餌の奪い合いが起きます。
そのため、熊の餌を奪ってるのは天候不順だけではなく、鹿やイノシシなどとの餌の取り合いになっていることを明記して、対策を講じる必要があると思います。
猟師が生活できる仕組みづくり
方針の【参考資料2】によれば、R6年度の狩猟免許所持者4,449人のうち、60代以上が2,311人 (51.94%) と過半数を占めています。高齢化は深刻です。
猟友会のハンターは、これを本職としている人は極めて少ないです。ほとんどが普段は他の仕事をしながら、または定年してのんびりと暮らしながら、狩猟を行っています。
様々な免許・許可・登録が必要であり、その費用もかかる。また、猟具をそろえたりメンテナンスしたりするのにも当然ながら費用と手間がかかります。さらに、実際に狩猟を行う際には命の危険も伴う。このような事実から、ハンターの数が少ないのも頷けます。
結論として、猟師が有害駆除や狩猟で生活が成り立つような仕組みを構築しなければ、担い手は減り続け、大型獣は増え続ける一方です。
ボランティア精神や使命感だけに頼るのではなく、危険な作業に見合った「職業」として成立するよう、県が本気で支援策を講じることが、最も効果的な対策となると考えられます。
参考資料に見る担い手の高齢化 (R6年度)
全所持者数: 4,449人
- 50代: 672人 (15.10%)
- 60代以上: 2,311人 (51.94%)
→ 50代以上が全体の約67%を占めており、若手・中堅の不足が明らかです。
まとめ|食べられる「餅」にするために
岩手県が示した「ツキノワグマ対策基本方針」は、対策の第一歩として重要です。しかし、これが「絵に描いた餅」で終わらぬよう、今こそ現場の実態に即した具体的な肉付けが必要です。
市町村や猟友会ごとの詳細なデータ分析、クマの生息地である森林行政との連携、観光客減少という経済問題への対策、そして何よりも担い手である猟師が報われる仕組みづくり。これらが伴ってこそ、人とクマのあつれきを軽減し、共存(あるいは棲み分け)していく道筋が見えてくるのではないでしょうか。
| 視点 | 現行方針の焦点 | 求められる追加視点(提案) |
|---|---|---|
| データ | 生息数調査(ヘアトラップ) | 市町村/猟友会別の「運営能力」分析 |
| 森林 | 緩衝帯の整備(棲み分け) | 広葉樹への転換支援、開発影響の考慮 |
| 経済 | 観光客への注意喚起 | 経済損失の試算、報奨金の明確な増額 |
| 生態系 | クマの個体数管理 | シカ・イノシシとの競合対策の強化 |
「熊の出没はいつまで続くの?」「いつまで熊に警戒して過ごさなきゃいけないの?」と不安を抱える人も多いでしょう。
行政による熊対策は、もはや待ったなしの最優先課題です。対策が後手に回り、このまま現状維持や議論・検討に終始すれば、来年、再来年と人身被害および農作物被害の拡大は避けられません。
我々が求めるのは、抽象的な議論や、実行を伴わない机上の対策構想ではありません。地域住民の生命と安全を守るため、現場の状況を的確に把握し、予算と人員を投じた実効性の高い対策を、直ちに講じることを強く求めます。
そして、私たち一般市民にできるのは、熊から自分や愛する人達の身を守ることです。
熊出没の情報が入るようにする(市町村からのお知らせやTV・新聞・Webなどのニュースを見る)、熊対策グッズを購入する、熊に遭ってしまったときの対応を知識として持っておく・・・これらが重要となります。